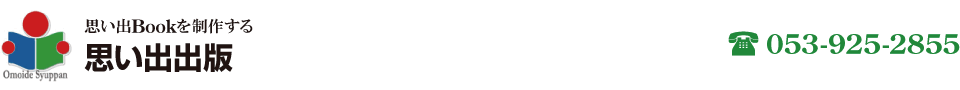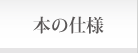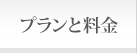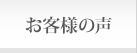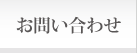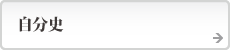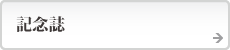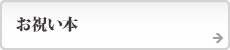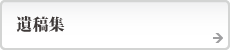「死生観教育」
1960年代にアメリカで行われるようになったデス・エデュケーションが、1980年代になって、日本でもその必要性が叫ばれるようになりました。特に、ターミナルケアにおいて、患者の心のケアに重要なものでありました。
そして、現在の日本は、団塊の世代が後期高齢者になる2025年問題を抱え、超高齢化社会を迎えようとしています。その中で、何年か前から終活がブームとなり、自分の死について考える機会が増えてきました。社会の安定とともに、死を冷静に考える人たちが増えてきていますが、多死社会に突入している日本人にとって、死の迎え方の問題は避けることができません。
今後は、過去の死生観と科学的に究明されていく人間の死について総合的に考え、一人ひとりが死生観を深めていくことになると思われます。死生観を深めていく上では、死の準備教育やターミナルケアについての理解を深めることは重要なことだと考えます。
「死の準備教育」
死について科学的に理解するとき、エリザベス・キューブラ・ロス氏が提唱した「死を受容するまでのプロセス」は欠かせません。ロス氏は著書『死ぬ瞬間』の中で、そのプロセスを「否認」、「怒り」、「取引」、「抑うつ」、「受容」の5段階があることを示しました。この説に対し、アルフォンス・デーケン氏は、第6段階として「希望」を加えています。
誰もが、このプロセスをたどるということではなく、中には、受容の段階に至る前に命を落とすこともあります。特に、注意すべきは過剰な不安です。ガンなどの難病を突然宣告されたなら、ほとんどの人は強い不安に襲われます。不安の強さからパニックに陥る人もいるでしょう。それを予防するためには、そうなる前、つまり医療にかかる前から死について考える必要があります。
では、いつ頃から考え始めれば良いのでしょうか。死についての理解は、10歳頃には始まっていると言われています。しかしながら、精神的に未熟な段階で強い不安を与えることには抵抗があります。かと言って、家族の死に遭遇した子どもが死を理解できずに強い不安を抱いたままでいることも事実です。
かつては、死が身近に存在していたことから、家族の死であっても自然現象の1つとして受け入れられていました。しかし、核家族化が進み、高齢者との同居が減ってきた背景もあり、子どもの頃だけでなく、成人になっても家族の死というものに遭遇することが減ってきました。
死の準備教育では、死別体験の重要性が説かれますが、その機会を得られないのが現状ではないでしょうか。医療の進歩とともに、死は自然なことでなくなっているような気がします。
「ターミナルケア」
今でこそ、医療現場での延命治療について問われる時代にはなりましたが、それでも、最期の迎え方については、様々な想いや考え方、そして、法律があり、必ずしも患者側の希望がかなえられるケースばかりではありません。大きな問題の1つは、医療現場の方々と患者側の死に対しての情報量や理解の差だと思います。医療現場の方々は、死への対応のプロですので、知識も理解も十分に備えています。それに対して、患者側は初めて死を迎えることが多いので、当然、差があります。
医療がここまで発達していなかった頃は、家で最期を迎えるのが当たり前であり、死には、地域や家の慣習が強く影響していました。亡くなる方もまた、その流れを理解し、自分の最期の在り方を見通すことができたのだと思います。
「終活」
かりです。
その火付け役になったのがエンディングノートではないかと思います。今では簡単に手に入れることができるようになったエンディングノートですが、出始めたばかりは、死をタブー視してきた日本人に受け入れられるのかどうかは分かりませんでした。その後、エンディングノートはシェアを拡げ、今では様々な種類が出回っています。エンディングノートを作ることによって、自分の死を見つめるとともに、大切な思い出を心に強く残すことができ、また、家族に対して不要な心配や迷惑を掛けないで済むという安心感が得られることが評価されたのだと思います。当然、家族の心の準備もできていきます。
1960年代にアメリカで行われるようになったデス・エデュケーションが、1980年代になって、日本でもその必要性が叫ばれるようになりました。特に、ターミナルケアにおいて、患者の心のケアに重要なものでありました。
そして、現在の日本は、団塊の世代が後期高齢者になる2025年問題を抱え、超高齢化社会を迎えようとしています。その中で、何年か前から終活がブームとなり、自分の死について考える機会が増えてきました。社会の安定とともに、死を冷静に考える人たちが増えてきていますが、多死社会に突入している日本人にとって、死の迎え方の問題は避けることができません。
今後は、過去の死生観と科学的に究明されていく人間の死について総合的に考え、一人ひとりが死生観を深めていくことになると思われます。死生観を深めていく上では、死の準備教育やターミナルケアについての理解を深めることは重要なことだと考えます。
「死の準備教育」
死について科学的に理解するとき、エリザベス・キューブラ・ロス氏が提唱した「死を受容するまでのプロセス」は欠かせません。ロス氏は著書『死ぬ瞬間』の中で、そのプロセスを「否認」、「怒り」、「取引」、「抑うつ」、「受容」の5段階があることを示しました。この説に対し、アルフォンス・デーケン氏は、第6段階として「希望」を加えています。
誰もが、このプロセスをたどるということではなく、中には、受容の段階に至る前に命を落とすこともあります。特に、注意すべきは過剰な不安です。ガンなどの難病を突然宣告されたなら、ほとんどの人は強い不安に襲われます。不安の強さからパニックに陥る人もいるでしょう。それを予防するためには、そうなる前、つまり医療にかかる前から死について考える必要があります。
では、いつ頃から考え始めれば良いのでしょうか。死についての理解は、10歳頃には始まっていると言われています。しかしながら、精神的に未熟な段階で強い不安を与えることには抵抗があります。かと言って、家族の死に遭遇した子どもが死を理解できずに強い不安を抱いたままでいることも事実です。
かつては、死が身近に存在していたことから、家族の死であっても自然現象の1つとして受け入れられていました。しかし、核家族化が進み、高齢者との同居が減ってきた背景もあり、子どもの頃だけでなく、成人になっても家族の死というものに遭遇することが減ってきました。
死の準備教育では、死別体験の重要性が説かれますが、その機会を得られないのが現状ではないでしょうか。医療の進歩とともに、死は自然なことでなくなっているような気がします。
「ターミナルケア」
今でこそ、医療現場での延命治療について問われる時代にはなりましたが、それでも、最期の迎え方については、様々な想いや考え方、そして、法律があり、必ずしも患者側の希望がかなえられるケースばかりではありません。大きな問題の1つは、医療現場の方々と患者側の死に対しての情報量や理解の差だと思います。医療現場の方々は、死への対応のプロですので、知識も理解も十分に備えています。それに対して、患者側は初めて死を迎えることが多いので、当然、差があります。
医療がここまで発達していなかった頃は、家で最期を迎えるのが当たり前であり、死には、地域や家の慣習が強く影響していました。亡くなる方もまた、その流れを理解し、自分の最期の在り方を見通すことができたのだと思います。
「終活」
かりです。
その火付け役になったのがエンディングノートではないかと思います。今では簡単に手に入れることができるようになったエンディングノートですが、出始めたばかりは、死をタブー視してきた日本人に受け入れられるのかどうかは分かりませんでした。その後、エンディングノートはシェアを拡げ、今では様々な種類が出回っています。エンディングノートを作ることによって、自分の死を見つめるとともに、大切な思い出を心に強く残すことができ、また、家族に対して不要な心配や迷惑を掛けないで済むという安心感が得られることが評価されたのだと思います。当然、家族の心の準備もできていきます。